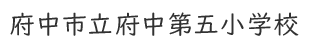校長ブログ26
校長ブログ070630 まずあやまり(全校朝会)
本日も朝からたいへんな暑さとなりました。そこで、全校朝会は、涼しい教室で行いました。今日は、あいさつの大切さについて、みんなで考えました。
「先日、床屋さんでご主人から聞いた話です。横断歩道で、信号待ちをしていたとき、小学生がよそ見をして走ってきて、いきなりぶつかってきたそうです。しかし、その子は、何も言わずに、走り去っていったそうです。「ごめんなさい」とか、ひとこと言ってくれたら、と寂しそうにつぶやいていました。
みなさんは、「おはようございます」という朝の決まった時間のあいさつはよくできます。でも、いつくるか分からないけれども、誰かが自分のために何かをしてくれたときのあいさつ、つまり「ありがとう」がすぐに言えますか。普段から、このあいさつが必ず言えていれば、床屋さんにぶつかったときに、とっさに「ごめんなさい」という言葉が出たのではないかなと先生は思うのです。
習慣が性格をつくるという言葉があります。私たちは、人とのつながりを大切にするために、あいさつをしますが、そのあいさつの習慣が、人から信頼されるあなたの性格をつくっているのです。だからこそ、誰かが自分のために何かをしてくれた時には、習慣のように必ず「ありがとう」が言える人は、人から慕われ、信頼されるようになっていくのです。ありがとうは、言われてうれしい言葉ですから。
さて、相手のことを考えることは、日本人のよいところで、江戸時代は「江戸しぐさ」という行動がありました。せまい道を、すれ違うときに傘を向け合う「傘かしげ」が有名ですね。せまい道を通るとき、相手に道を譲ることも礼儀とされてきました。相手のことを考えると、みんな仲良く暮らせるのです。先日ある中学校で、こんな取組をしていました。「現代版江戸しぐさを考えよう」という取組です。
リュックを背負って電車に乗るとき、みなさんはどうしますか。そうです。後ろの人に当たらないように、相手のことを考えて、おなかに「だっこ」するように背負いますね。その中学校では、これを『カンガルー』と名付けました。覚えやすいですね。
床屋さんの話のように、人とちょっとぶつかってしまった、悪かったと思ったときにどうしたらよいでしょうか。その中学校でつくった江戸仕草の名前は、ズバリ、『まずあやまり』です。どうですか。先生は、とてもよいネーミングだと思いました。何をおいても、まずは、あやまるという、この『まずあやまり』がみんなの習慣になって、すぐに「ごめんなさい」とひとことが言えていれば、つまらないけんかも減るでしょう。床屋さんも、悲しい気持ちにはならなかったと思います。みなさんはどう思いますか。
みんなで仲よく生活したい。これはみんなの願いです。梅雨になって、教室で過ごすことが多いです。「ありがとう」を言うチャンスはたくさんあります。あいさつを習慣にしましょう。そして、いつどんなときでも、「ありがとう」や「ごめんね」が言える人になりましょう。お話を終わります。」